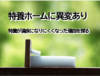カテゴリー ≫ 老人ホームの選び方
有料老人ホームの費用はいくらなのか?
有料老人ホームの費用はいくらなのか?
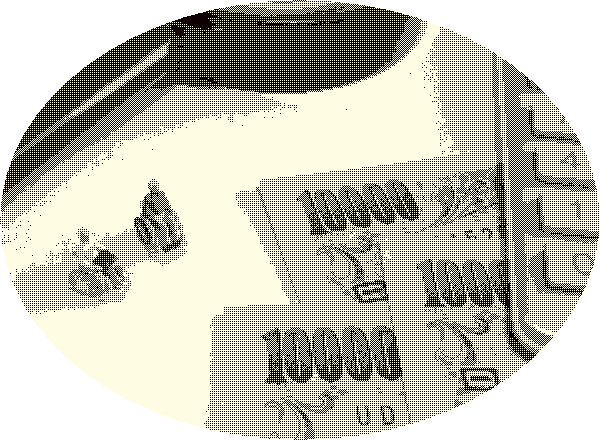
有料老人ホーム選びの指標となるのは、大きく分けると「場所」「内容」「費用」ではないでしょうか。今回はそのうちの「費用」にクローズアップしてみようと思います。ピンからキリまでとはよく言いますが、その差は一体何なのか。相場、また、最低ラインはどのくらいなのか。何にいくらくらい費用が掛かっているのか。実際の費用も例に挙げながら見ていきます。
まずはともかく基本料金
まず、パンフレットやホームページにも記載されている基本料金についてです。入居時費用と月額費用が記載されていると思います。今回は、この「月額費用」についてお話しさせていただきます。
ほとんどのホームでは
- 家賃
- 管理費
- 食費 の合計を、基本料金として定義しています。
家賃とは?
費用の差が出る大きな要因の一つが家賃です。不動産物件と同じく、都心の地価の高い場所や駅近など便利な場所にあるホームの家賃と、地方や不便な立地のホームの家賃とを比べると、大きく差が出てきます。
比べてみよう!
同じ会社が運営しており、サービス内容も同じホームの家賃を比較してみます。
目黒区内 :45万8,000円
さいたま市内:13万5,000円
「場所」「内容」「費用」のすべてが合致する施設はなかなか無い中で、「同じ内容なら安い方が」と少し離れた地方を選ぶ方もいらっしゃいます。とはいっても、緊急時にかけつけられる足があるかどうかも大事なポイントです。また、面会時などの交通費が、近隣の少し高い施設との差額分だけ、結局かかってしまう、といった場合もあります。
比べてみよう!
家賃の差が出る立地以外の要因としては、もともとあった建物(社員寮や病院など)を改装している為、費用が抑えられるケースがございます。
同じ会社が運営しているホームで、新築型と改装型の家賃を、同じさいたま市内で比較してみます。
新築型(北区):86,250円
改装型(中央区):67,000円
改装型は、建物は古いですが、提供サービスは同じです。窓が少ない、廊下が狭い、部屋が狭い、なんとなく暗い、といった、古いことによるマイナス面もあります。しかし、建物が介護をするわけではありません、あくまでも、「人」「内容」です。中には、新築でホーム用に建築していますが、年季が入ってきてしまったため、価格改定で費用を下げるホームもあります。
ハード面で費用が下がるケースとして、もう一つ挙げられるのが、個室ではなく相部屋、病院のような多床室であることで、家賃を抑えられるホームです。ただ、最近では基準が変わり、多床室は新設することができなくなっています。その為、民間のホームで多床室のものは、首都圏では数えるほどしかありません。
他にも、リハビリルームやカフェスペース、シネマルーム、カラオケルームなど、共用スペースが多く、敷地の広いホームは家賃が高い傾向にあります。家賃の最大値はまさにキリがありませんが、最低値は、個室で7万円前後、多床室で5万円前後になります。

管理費とは?
この金額は、ホームによって表記や内容が変わります。
例えば、水光熱費。個室と共用部を併せて一律で請求しているホームもあれば、基本料金には共用部のみが含まれており、個室の水光熱費は個別でメーターでの請求としているホームもあります。共用スペースが多いと、その分水光熱費も上がりますし、維持費も多くかかります。
運営のためのスタッフの人件費も含んでいる場合があります。例えば、送迎や掃除など、専門のスタッフを別途配置している施設では、管理費が高い傾向にあります。
また、後述の食費のお話にも関わってきますが、厨房管理費を「管理費」に含むか「食費」に含むかについても、施設によってまちまちです。厨房管理費は2万円前後が平均ですが、管理費と食費のどちらに含まれているかによって、料金表の見た目の費用差は感じられると思います。
内訳は、殆どのホームが料金表に記載がありますので、入居検討前には必ずチェックしてみてください。
ホームごとの表記と内容によって幅がありますが、低価格帯のホームで3万円前後、高めのホームで10万円前後です。
食費とは?
大体平均で1食500円前後、3食30日で月5~6万円のホームがほとんどです。食材費は地域問わず大きな差がなく、高級ホームであったとしても食材費に関しては同じくらいです。先ほどもお話した厨房管理費の有無によって見た目の差は出てきますが、食材費の実質の差はそこまでありません。
ホームによっては定期的に、特別食、イベント食といった、別料金を徴収し希望者に特別な食事を提供しているところもあります。これは基本料金には含まれていません。頻度や費用は確認が必要です。また、アラカルトメニューといって、毎日決まっている献立以外に、選択可能なメニューを常設しているホームもあります。カレーやうどんなど、簡単なものは基本料金内の場合もあれば、特別メニューなどは差額を頂いて提供している場合もあります。
その他に掛かる費用とは何か?
月額を計算するうえで、基本料金以外にかかる費用があります。それは、介護度によって金額が前後する「介護保険の自己負担分」です。問合せの中には、基本料金の中には、介護費用が含まれていると考えているお客様も多くいます。介護度によって、お手伝いの量や内容が変わってくる為、基本料金とは別に負担は必要です。
ご自宅で、訪問ヘルパーやデイサービスなどを利用する際は、サービスごとに単位数が決められている為、介護度に応じた単位数の上限内で収まるよう、ケアマネージャーにケアプランを立ててもらいます。ケアプランで組み立てた時間ごとに、スポットでサービスを行ないます。
住宅型老人ホームやサ高住と介護付き老人ホームとの料金の違いとは
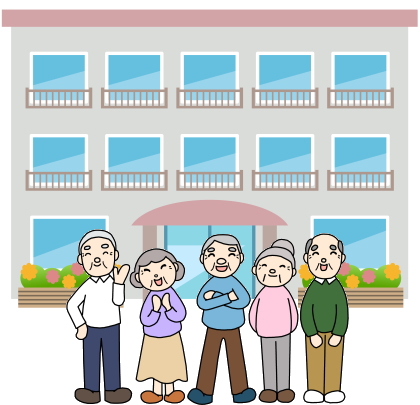
「住宅型有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」では、在宅時と同じように、サービスを単品で組み合わせて利用をしていきますが、『介護付き有料老人ホーム』は少し異なります。サービスの利用の有無を問わず、介護度に応じた上限の単位数全てをお支払することで、スポットで時間ごとのサービスではなく、臨機応変に介護を行なえます。
掃除、洗濯、入浴介助、食事の提供や介助、お着換えやお手洗いの誘導といった、生活を送るうえで必要なサービスは、この自己負担分の金額の中に含まれています。
在宅同様にケアプランは作成し、それに沿ってお手洗いの誘導や食事介助など、時間をある程度決めて行なっていますが、プランとプランの間の空白の時間をカバーできるのが介護付き有料老人ホームです。
介護付き有料老人ホームの自己負担分の費用は、施設によってサービスの内容により加算の制度があります。例えば、看護師の夜間の配置やリハビリの実施など、サービスの内容によって加算されるため、施設によっては数千円前後することもありますが、平均では下記のとおりです。
| 要介護① | 要介護② | 要介護③ | 要介護④ | 要介護⑤ |
| 16,355円 | 18,362円 | 20,490円 | 22,435円 | 24,533円 |
(厚生労働省「第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料」:資料2「介護報酬の算定構造」より)
上乗せ介護費用とは
ホームによっては、基本料金の中に「上乗せ介護費用」を頂いている施設がございます。これは、基準の3:1の人員配置以上に、手厚くスタッフを配置している際の、人件費です。
消耗品費とは
また、オムツやトイレットペーパー、ティッシュ、歯磨き粉など、消耗品は別途使った分だけの請求になります。施設によってオムツ代が固定費の所もあれば、行政の支給を受けられる場合もあります。
自費サービス
介護保険の自己負担分でできるサービス以上に、何か個別でサービスをご利用されたい場合、施設独自の自費のサービスを行なっている場合があります。
例えば、通院時の付き添い送迎に関して。中には基本料金内に含まれるので、無料で行なっていることを売りにしている施設もあれば、時間ごとに費用を徴収する施設、またはそもそも通院の付き添い送迎を行なっていない施設もあります。
また、お風呂の回数に関しても、施設毎に異なります。基準で定められているのは、週2回ですが、基本料金内で週3回のところもあれば、有料で回数を増やせるところ、2回以上はできないところ、などがあります。マッサージやリハビリなども同様に、基本料金内、有料、実施無しと、施設によって様々です。
国で定められた基準以内の介護サービスに関しては、自己負担分が原則ですが、+αのサービスは、同じ「基本料金」の表記でも、そこに含まれるサービスは細かく異なります。
最後に
条件を入力すると、それに合致したホームが一覧で出てくる検索サイトがたくさんあるかと思います。しかし、その絞り込んだご予算、これはあくまでも、料金表に記載されている「基本料金」に過ぎません。施設によって、その他に掛かる金額や、基本料金内に含まれているサービス内容は様々です。絞り込みで選択肢を狭めてしまう前に、求めるサービスが叶う施設をお探しの際は、専門の相談員に聞いてみるのも、施設探しの方法の一つだと思います。
相談サポート室 室長代理 浅間 勝之
老人ホームとグループホーム
老人ホームとグループホーム

こんにちは。みんかい相談員の入江です!
実家で暮らしている自分の親が、もう一人暮らしは難しいだろうなと感じる時はどんな時でしょう。身体的な衰えから階段や段差が生活の障害となり、転倒することが増えて怪我することが多くなった時。時には骨折して入院し、リハビリしてやっとこさ退院して自宅に戻ったはいいけど、また転倒を繰り返してしまう。入院のたびにベッドで寝たきりの時間を多く過ごすので、さらに筋力を低下させてしまうという悪循環におちいり自宅での生活に不安や危機感を覚える時。あるいは、認知症を発症してしまい、物忘れの症状が日常生活に支障をきたす時ではないでしょうか。
認知症と物忘れとの違い
親が認知症となると、どんな風に困ることとが増えていくのでしょう。
まず、認知症は「老化によるもの忘れ」とは違います。もの覚えが悪くなったり、人の名前が思い出せなくなったりしますが、このような症状は「老化によるもの忘れ」によるものだと言われています。認知症は、何らかの病気によって脳の神経細胞が壊れることで引き起こされる症状や状態のことをいいます。認知症が進行すると、だんだんとものごとを理解する力や判断する力がなくなり、日常生活に支障が出てくるようになります。
例えば、ご飯を食べたことを自覚しているけれども、メニューが思い出せないというのは加齢によるもの忘れです。でも、ご飯を食べたこと自体を忘れてしまっている場合は認知症の可能性があります。
自宅の鍵やお財布、銀行の通帳などの貴重品をなくしてしまったとき、加齢によるもの忘れがある人は、自分で努力して見つけようとします。認知症の方は、誰かによって盗られたなどと他人のせいにしてしまいます。
認知症には「中核症状」と「行動・心理症状」のふたつの症状があると言われています。「中核症状」とは、脳の神経細胞が壊れていくことによって引き起こされる「記憶障害」、「見当識障害」、「理解力・判断力の障害」、「実行機能障害」、「感情表現の変化」などが挙げられます。
「記憶障害」は、新しいことを記憶できず、ついさっき話していたことも思い出せなくなります。昔の話だけはしっかり覚えているんです〜なんていうご家族様もいらっしゃいますが、認知症が進行すると覚えていたはずの記憶も徐々に失われていきます。
「見当識障害」は、時間や日にち、曜日、季節の感覚が薄れ、自分がどこにいるかなどの基本的な状況把握ができなくなります。外出先で自宅への帰り方がわからなくなったり、帰り道がわからなくなることもあります。自分の年齢や家族のこと、家族の生死に関する記憶も薄れていきます。
認知症の具体的な症状とは
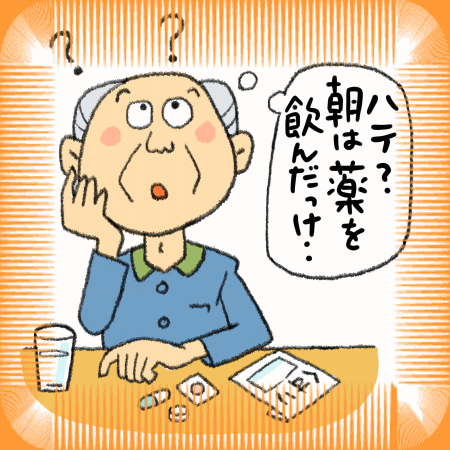
「理解力・判断力の障害」は、思考スピードが低下してふたつ以上のことが重なると、話している相手が誰かわからなくなるなど、些細な変化などいつもと違う出来事に混乱をきたすなどの症状が起こりやすくなります。自動販売機や自動改札、銀行ATMの前でまごついたりしている方は、もしかしたらこうした認知症による症状が影響しているかもしれません。
「実行機能障害」とは、買い物で同じものを何度も購入してしまったり、食事に支度ができなくなったりなど自分で計画を立てられなくなったり、予想外の変化に対応できなくなるなど物事をスムーズに進められなくなります。
「感情表現の変化」については、その場の状況がうまく認識できなくなることにより、周囲が予測しない思いがけない感情の反応を示すような症状が出ます。急に泣き出してしまったり、怒り出してしまったりする高齢者は認知症である可能性もあります。
「行動・心理症状」とは、本人がもともと持っている性格や環境、人間関係など様々な要因が絡み合って起こるうつ状態や妄想といった心理面・行動面の症状になります。具体的には、今まで出来てきたことがうまく出来なくなっていることを自覚し、自信を失って全てを面倒になってしまう意欲低下や、自分のしまい忘れが原因だったとしても、他人が泥棒に入った、嫁が盗ったなどの物盗られ妄想などが挙げられます。
グループホームという施設もある

このような認知症の方には、老人ホーム紹介センターがご提案するのは「老人ホーム」のほかに「グループホーム」がございます。
グループホームは、まず認知症に特化している施設です。そのため、入居するにあたっては医師から認知症と診断されていることが条件となります。そのほかの入居要件は要支援2から要介護5までとなります。地域密着型サービスといわれ、グループホームのある市区町村に住民票のある方が入居対象となります。入居者9名を1つのグループ(ユニット)として、家庭的な雰囲気の中で認知症の高齢者が共同生活を送ることにより、認知症の症状の進行を穏やかにすることを目的としています。
認知症の進行を穏やかにするとはどういうことかといいますと、入居者には掃除や洗濯、食事の準備や後片付けなどの身の回りのことを自分でしてもらい、また出来ないことは助け合いながら生活することで日常生活そのものがリハビリとなるよう工夫しているということです。
ただ、9名の入居者に対して介護職員も1〜2名程度なので基本的に自立し生活ができる方が入居対象となり、そもそも寝たきりであったり終末期を迎えられている方は入居の対象となりません。介護士(ヘルパー)は24時間常駐しますが、看護師がいないので看取りの態勢が取れないことがあるからです。
住み慣れた地域で、少人数で共同生活を送るのでコミュニケーションが取りやすく、馴染みやすい関係を築きやすいです。また、人の入れ替わりも少なく、入居者や介護士の顔も覚えやすく身近に感じる環境のため、人の入れ替わりや新しい人の名前を覚える認知症の方には混乱をすることも少なくメリットがあります。
デメリットは、どうしてもスタッフの人員配置から人手に限りがあり、介護量が増えてくると退所を促されてしまう可能性があるということです。前述したとおり看護師も常駐しないため看取りの対応をしていないところが多いです。家庭的でアットホームな雰囲気を好む方には非常に向いているとも言えますが、入居対象者となる方の持病や状況によってグループホームが合う、合わないといった問題も出てきます。ご自身の親御さんの状況などを把握しながら検討していく必要があります。
一般的な老人ホームは24時間ヘルパーがホーム内に常駐し、また看護師も昼間の時間帯は毎日いるという体制です。入居者3名に対して平均して1名のスタッフが配置されるような人員居配置基準というものも設けられているため、グループホームよりは身体的・医療的な介護サービスを提供できる環境がございます。ただ、居室数は一般的に60~70室前後となっており、グループホームよりも部屋数も多く大所帯というイメージになります。
また、小規模なグループホームを心地よいと感じられるかどうか、ご入居の対象となられる方の性格にもよるところがあります。認知症を患っているからといって、必ずしもグループホームが適しているとも言えない場合があります。そもそも共同生活を苦手とされる方は、小規模で入居者同士の距離感やスタッフとの距離感が近すぎることを嫌がる場合もございます。
どのようなホームがご自身の親に合うのだろうかと迷われたときは、まずは老人ホーム紹介センター・みんかいへお問い合わせください。お手伝いさせていただきます!
みんかい首都圏相談室 相談員 入江 佳代
老人ホームへ入居するべきか│失敗しないための5つのポイント
人生の選択肢の一つとしていずれは老人ホームへの入居を考えている人が増えています。
入居を検討する際に押さえるべき5つのポイントについて解説します。
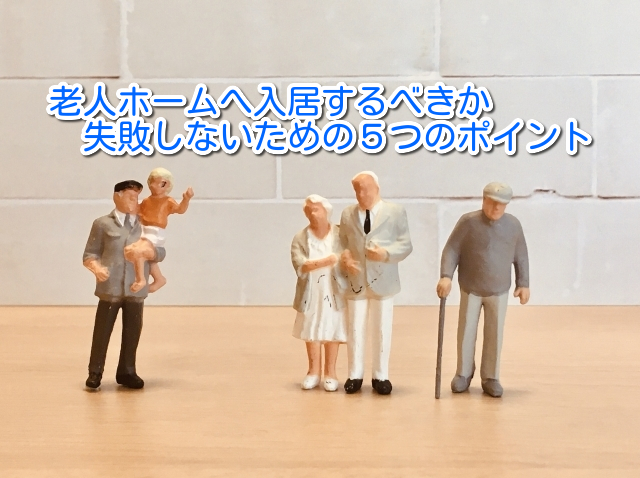
1.老人ホームの入居条件
一般的には60~65歳以上となっています。「介護付有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」では、一般的に入居条件をおおむね60歳以上としています。そのため、一般的な定年後の65歳以上であれば、ほとんどの老人ホームでは条件に当てはまっているということになります。
ほかにも、「特別養護老人ホーム」や「グループホーム」なども、条件が原則65歳以上となっています。
但し、「特別養護老人ホーム」や「グループホーム」では年齢に加えて、要支援や要介護などの介護認定を受けていることが必要条件に含まれてきます。
介護施設は先ほどご紹介した施設以外にも数種類があり、その施設の入居条件も各々異なっています。
60歳未満でも入居可能な老人ホームも存在はしています。
介護サービスの提供がないサービス付き高齢者向け住宅や健康型の有料老人ホームなどは、60歳未満の方でも入居できることがあります。60歳未満の方でも、生活スタイルを考え、年齢をベースに、受け入れ可能なところを探してみるのも良いでしょう。
また、60歳未満の方でも特定疾患により要介護・要支援認定を受けている方であれば、老人ホームに入居し介護サービスの提供を受けることも可能です。
ほかにも、高齢者向けのマンションなどは、入居条件に一定の決まりがない場合が多いため、60歳未満であっても入居が可能となっています。
高齢者向けのマンションなどでは設備が充実したものも多く、ジムやプールなどの設備が併設したり、有料で洗濯や掃除などのサポートや病院などへの送迎といったサービスを提供しているところも少なくありません。
但し注意しなくてはならないことは、やはり介護施設ではないので、介護などが必要になった場合には、通常の在宅での介護と同様に、介護保険サービスやご家族の協力などサポートが必要になります。
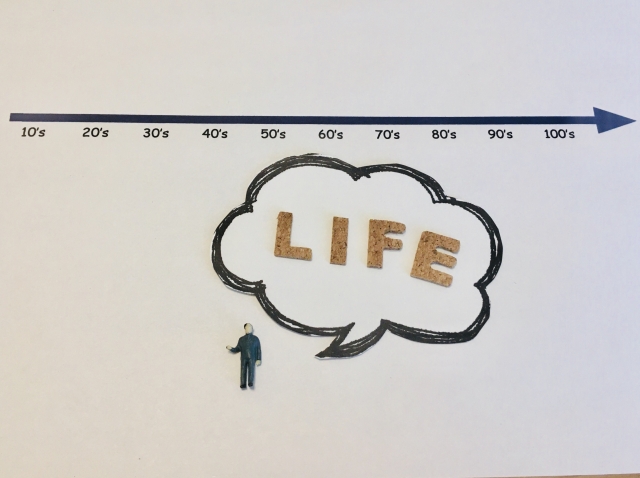
2.老人ホーム入居者の平均年齢
一般的に入居条件を65歳以上としていますが、実際に利用している方々は何歳ぐらいから入居しているのでしょうか。
社団法人全国有料老人ホーム協会の情報によると、平均年齢は80歳代~90歳代の方が多いように見受けられます。
比較的元気な60歳代~70歳代のうちは在宅(ご自宅)で暮らし、70歳代~80歳代に入ったあたりから、今後の生活の場所(終の棲家)として入居を考える方が多いのではないでしょうか。
但し、老人ホームへの入居を考えている方々の全てが、介護を必要としているとは限りません。

3.老人ホームに入居する目的
老人ホームというと、介護が必要になり日常生活に支障をきたすなどの問題が出てきた場合に、その方を誰もお世話ができないなどの事情が現れてきたときに「仕方なく介護をしてもらうために入居する場所」というイメージがあるかもしれません。しかし、老人ホームへ入る目的は、必ずしもそれだけではありません。例えば、過去に親や身内の介護を経験しており、自分の子ども達に同じ思いをさせたくないという気持ちから介護が必要になる前に自ら老人ホームでの生活を決める方もいらっしゃいます。
入居する目的は、大きく分けて次の2つになると思います。
日常生活の介護をしてもらうための場所
例えば、親が寝たきりや日常生活を1人で送るには支障が出るレベルの介護が必要となった時に、子どもが働いていたり子育て中の場合、親の介護をするのは決して容易ではありません。
また、介護を受ける親としても、満足するような介護を受けることができず、ストレスに感じることもあるでしょう。そのような在宅介護の限界から必然的に、老人ホームへの入居を決めるケースです。
老人ホームを考え出すきっかけとして、親のためだけではなく介護を担う家族の負担を軽減するということも目的となることが多いです。
セカンドライフを送るための場所
介護が必要となってから入居を決める方がいる一方で、元気なうちにセカンドライフを送る場として入居を考える方もいらっしゃいます。このような方にとっては、老人ホームは趣味やサークルなどを楽しむための場所として捉えています。高級ホテル暮らしを思わせるようなさまざまなサービスや設備を整えているところも増えているので、今後は「セカンドライフを送るための場所」としてこのような老人ホームへ入居する高齢者の方々も今まで以上に増えてくるかもしれません。老人ホームの種類によって、楽しめる趣味やイベントの内容も異なります。
自立型のホームによっては、オペラなどを始めとする各種コンサートや鑑賞会や趣味の会など、多彩なイベントを企画し、入居者様の充実したセカンドライフをサポートしている施設も少なくありません。
充実したセカンドライフを送るための場所として老人ホームを探す場合は、その老人ホームではどのような特徴があり、どのような生活が送れて、自分のイメージしている生活と合致しているのか、また、できるのかを確認しておく必要があります。

4.いつから老人ホームを探し始めるのが良いか
老人ホームの多くは「入りたい」と思っても、すぐに入居ができる施設ばかりではありません。
入居に関する条件や年齢に達していても、「いざ探し始めたら思ったように入居できなかった」というのが実情です。老人ホームを探すには、思っている以上に時間とある意味、体力が必要です。一般的には、見学から入居までに1ヶ月半~2ヶ月程度を要しますので、そのことを念頭に早めに探し始めることが基本です。
希望の老人ホームに空室がない場合は、入居までの期間が通常よりもさらに長くなるので、その点についても留意しておく必要があります。
ホーム探しは期間がかかるということ以外にも、入居者本人またはご家族が年齢を重ねれば重ねるほど、老人ホームを探すこと自体が重荷になってきます。そのため、妥協のない老人ホーム探しを行うためには、心も体もできるだけ元気なうちに準備を始めておくことをお勧めします。
また、老人ホームへの入居を早めることで、他の入居者や施設のスタッフとの関係構築や交流の時間に充てられたり、いざ介護が必要となった場合や介護度が上がった場合など、スムーズに対応してもらえたりなど、さまざまなメリットがあります。
老いて自分では何もできなくなってから入居するのではなく、たとえ介護状態であっても、施設での生活を楽しめるうちに入居することがベストだと考えています。

5.老人ホーム入居を考える上で大切なこと
今後の人生計画を立てる上で、老人ホームを選ぶ際は、何歳からとか、身体がどのような状況になったら入居するかということも大事ですが、「自分らしい生き方や生活が送れるか!!」を大切に考えて選ぶということが一番重要です。
それには、ホームの日常の雰囲気、他の入居者やスタッフとの相性、介護サービスの有無や内容、行われている年間行事、月額の費用や介護保険以外のサービスに対する相場感など、さまざまな面で判断する必要があります。
(文:みんかい総務部 内藤)
老人ホーム探しの極意
老人ホーム探しを皆様は、実際に当事者として行った事がありますか?老人ホームって、そもそも見た事がない、イメージがわかない、また、どのような生活を皆さん老人ホームでされているのかわからない方が、ほとんどではないでしょうか?老人ホーム探しは、私も、有料老人ホーム紹介センターみんかいに入るまで、経験した事はありませんでした。老人ホームがどんな場所か、見当もつきませんでした。

老人ホームは人生の墓場?
老人ホームというキーワードを聞いて、皆様は、まずどのようなイメージをお持ちでしょうか?今もまだ、暗いイメージ、入居すると外出、自由がない、寝たきりの方が多い、人生の墓場みたいなイメージを持っている方は、この老人ホームが多くなった時代にも、少なからず、多いのではないかと思います。
そもそも老人ホームという名前が、イメージを悪くしているのではないでしょうか。高齢者住宅、高齢者ホーム、高齢者ハウス、シニア住宅、シニアホームなどの方がイメージが良いように思えます。
老人ホーム探しの難しいところとは
老人ホーム探しは、人生の中で、1回あるかないか、なかなか頻繁に起こりうる事ではありません。だから、実際、私たちの有料老人ホーム紹介センターに相談される方は、はじめての経験であり、右も、左もわからなく、慌てて相談に来られる方が、大半を占めております。まさか、自分が親の老人ホーム探しをするとは、夢にも思っていなかった、初めての経験で、何をどう探せば良いのかわからない、インターネットで調べたけど、どのように探せば良いかわからないなどの、困惑して、面談に来られる相談者が多いのが現実です。
旅行で宿を探す、結婚して家を探すなどとは、まったく違い、老人ホームという内容がわからない住宅を探す事、また、不動産会社みたいに、どこに頼って探せば良いかイマイチよくわからない事が、一番の難しさではないでしょうか。有料老人ホームの紹介センター自体まだ、世の中に知られておりません。

老人ホーム探しは、時間もかかります。時間をかけないと、良い老人ホーム探しはできません。インターネットで、検索して、簡単に探せると思ったら大間違いです。たとえ、インターネットの検索サイトで、探し出せたとしても、一番大切な、住まいとしての(生活する上での)ミスマッチを起こしてしまうのではないでしょうか。実は、老人ホーム探しで一番難しいのは、いかにミスマッチを防ぐ事ができるかが、ポイントです。
ミスマッチの代表的な種類は、①雰囲気(生活)のミスマッチ、これは、とても大切な事で、パンフレットではなかなかわからない内容です。レクリエーションなどが盛んで楽しみがあり、外出できると思って入居したホームが、実は、ほとんど、ご病気で寝たきりの方ばかりで、レクリエーションは、パンフレット上のもので、実際は、ほとんどやっておらず、入居者のADLが落ちてしまったという話は良く聞きますし、その逆もあります。また、老人ホーム探しの中でのミスマッチで、②費用のミスマッチがあります。実は、月額がこんなにかかるとは思っていなかった。また、③医療対応、リハビリ、食事など、しっかりと見学時などに見極めないと、想像もできない、ミスマッチに遭遇して、第二の人生の老人ホームでの生活が、窮屈になるのではないでしょうか。
老人ホーム探しで、一番気をつけなければいけない事は、今上記に記しましたように、人生で一回あるかないかの出来事なので、上記を含む、さまざまなミスマッチをいかに少なくするかが、大切なポイントではないかと思います。まったく経験がない皆様は、そのミスマッチすら思い浮かばない場合が多いので、入居してから、こんなイメージではなかった、と後悔する方が多いので、私たちの有料老人ホーム選びの相談員が、老人ホーム探しのお手伝いをさせていただいております。
3マス(鱒)の重要性
上記のミスマッチを防ぐために、みんかいでは、三マスというキャラクターを作りました。
この三マスは、現在は大阪相談室のロゴになっておりますが、相談員の基本姿勢が記されております。三匹の鱒をモチーフに、見ます、聞きます、話しますという相談員の基本姿勢がロゴになっております。
- 見ますは、有料老人ホーム紹介センターの相談員は、ホームの表面上の部分と、隠された裏の部分をしっかりと見て、お客様にありのままを伝える事が大切であり、
- 聞きますは、お客様のホーム探しに関する困りごと、不明な事、ご要望などをしっかりと聞きますという思いを込めており、最後の
- 話しますは、相談員が、ホーム選びで必要な情報をお客様である相談者に、話しますと、いう意味と、ホームの見学などにお客様と同行して行った際に、お客様が言いそびれた大切な質問や、お客様が話しずらい、もしくは言い忘れてしまった質問を、話すという意味もあります。
この3マスの考えは、老人ホーム探しには、とても大切な内容です。また、老人ホーム探しの中の老人ホームは、未だに、イメージを悪く創造してしまう方が多いかと思いますが、最近の老人ホームは、冒頭にあげたように、比較的明るく、多様化したサービスを売りにしている有料老人ホームが多々でてきております。
ときめきホーム選びの重要性
老人ホーム探しのキーワードで、冒頭にも書きましたが、老人ホームのイメージは、未だに暗いイメージをお持ちの方が、多いのは事実です。
私たち、有料老人ホーム紹介センターみんかいのロゴには、先ほどの3マス以外に、トキオとトキコのときめきホーム選びというトキをイメージしたロゴがあります。
老人ホームは、暗いところばかりでなく、楽しみがいっぱいあるところ、明るいところ、ミスマッチの少ない、有料老人ホーム選びをする事で、老人ホームに入居した後でも、第二の人生を楽しいものに、活き活きと生活してほしい、そのためにも、私ども、有料老人ホーム紹介センターの相談員が3マスを駆使して、ホーム選びのお手伝いをさせていただく、ときめきホーム選びというロゴが完成しました。
私たちの相談員業務は、お客様の大切な時、第二の人生をホームで活き活きと過ごすための時(トキ)にかけております。老人ホーム探しをするときに、少しでもお手伝いができ、第二の人生を楽しくすごせるように、ときめきホーム選びの精神は忘れずにいたいです。
ミスマッチが起きる理由
老人ホーム探しでは、具体的に、上記のミスマッチをいかに最小限に抑える事が大切であり、老人ホーム探しでは、いくつかの下記に列挙する大項目がポイントとなってきます。いつ入居するのか?入居のタイミングによって、選ぶ老人ホームの分類が変わってくる。介護付き有料老人ホームなのか、住宅型有料老人ホームなのか、サービス付き高齢者向け住宅なのか、グループホームなのか?お元気(自立)から入るホーム選びと、介護が必要になってから探すタイミングでの老人ホーム探しは、選び方が180度違ってもおかしくありません。
老人ホーム選びのポイントとは

次に、老人ホーム探しでは、お身体の状況によって、今の既往歴と病気、またその病気が今後どのように進行していくのかによっても、老人ホーム探しのポイントは変わってくるので、医療面の対応に関しては、必要以上に注意して対応する必要があります。協力医療機関の診療科目など大切になってくるのではないでしょうか。また、服薬から、インスリン、透析になったとしても、家族に負担をかけることなく、継続して住まい続けられる事が大切です。
また、老人ホーム探しでは、費用の項目も大切な項目です。費用はトラブルにも繋がりやすいケースが多くあり、例えば「想定していた以上の費用がかかってしまい月額費用の追加費用が払えない」「返還金の項目があるが返還されない」などのトラブルがあります。費用に関してどんなリスクや、トラブルがあるかは、今一度、確認しておくべきです。
次に老人ホーム探しでは、なぜ老人ホームにはいるのか?目的はとても大切になります。今では、特別養護老人ホームの待機として、有料老人ホームの入居金ゼロ円プランを活用して、待機しながら入居を考えたり、冬や、夏の暑い間を目的にショートステイやミドルステイを活用する利用の仕方もあるので、目的により、選ぶ施設も内容も変わってきます。
老人ホーム探しでポイントとなるのは、運営母体やその運営母体の教育体制また、ホーム長やそのホームで働く、看護師や、生活相談員の人柄、介護やその運営会社の理念なども参考にする必要があります。どんなにすばらしい理念やポリシーを運営会社が掲げていたとしても、実行されていなかったり、絵に描いた餅であれば、意味がないので、老人ホームを探す際には、体験してみたり、体験する時間がない場合は、有料老人ホーム紹介センターの相談員に聞いてみるのも良いのではないでしょうか。

以上、老人ホーム探しにおいては、時間もかかり、数多くの経験をした、自分に合う相談員を見つけ、できる限り、ご希望、ご要望を伝えて、ホーム選びをする事が、良い老人ホーム探しができるのではないかと思います。老人ホームも日々、顧客ニーズに合わせて変化しており、また、有料老人ホーム紹介センター相談員もその時流にあった、老人ホーム探しをする必要があります。
いずれにせよ、インターネットが発達した今、安易に検索サイトでひっかかったホームを選択して、入居するのではなく、実際目で見て、体験して、体験する時間がないのであれば、様々な事例を体験している経験豊富な相談員に相談して、老人ホーム探しをする事をお勧めします。老人ホーム探しは、有料老人ホーム紹介センター探しから、また、入居希望の相談者と気の合う相談員探しから始める事が、失敗しない、老人ホーム探しの近道ではないでしょうか。
(文:みんかい法人事業部 内山)
有料老人ホームの種類と費用
老人ホームと一口に言っても多種多様。様々なタイプのものがあります。さらに、入居基準も様々、費用も様々です。しかも、わかり難いときています。時間の無い現代人の皆様が、これらのことを正しく理解し、有益に活用していくことは、実は至難の業になります。
そんな時は、私たちのような紹介センターを活用するべきです。ということが本コラムの主張ですが、けしてこれは、みんかいを使ってください、と言うことではありません。素人の人が、一筋縄では理解することができないもの。それが老人ホームなのです。
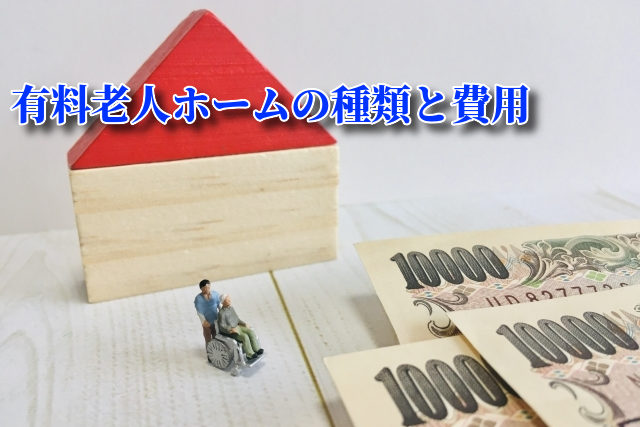
老人ホームを探した事はありますか?
たいていの人は、有料老人ホームに関わる機会は、ほぼなく、必要に迫られて探さざる得ない事がほとんどかと思います。いざという時のために、知っておいて損はない有料老人ホームの種類と費用、選ぶ時のポイントについて説明したいと思います。
有料老人ホームを探す前に、まずは「有料老人ホームへの入居動機」を確認しておきましょう。「在宅生活が不安なので、24時間の介護サービスを受けたい」「退院後、自宅に戻れないので有料老人ホームでケアを受けたい」「同年代の人たちと一緒に楽しく生活したい」など、人によって理由は異なります。
理想の有料老人ホームの探し方は、「理由」によって違ってくるため、入居動機を明確にしておくことが大切です。 入居動機がはっきりすれば、それに沿って有料老人ホームに求める優先順位を定めることができます。
たとえば、入居する際の費用や月額利用料といった料金体系、立地、受けられる介護・医療サービス、食事内容、日々の生活を豊かにするレクリエーションやリハビリテーションなど、入居するうえで何を優先するのか、自分の条件を明確にしておくことが重要です。

老人ホームには入居資格がある。
有料老人ホームは誰でもが入れるわけではなく、入居資格が設けられています。資格はホームごとに異なっており、入居時に要介護認定を受けていないと入居ができないホームもあれば、入居時に介護認定が「非該当(自立)」の人でも入居できるホーム、逆に「非該当」の人しか新規入居ができないホームもあります。また、65歳以上などと年齢制限が設けられている場合もあります。
有料老人ホームには「介護付き」と「住宅型」があります。違いは、サービス体系が異なるだけで料金や提供されるサービスに大差はありません。それよりも、各ホームのスタッフの人員体制、部屋や共用部分の広さ、立地、食事、レクリエーションなどによって、入居時にかかる費用や月額利用料に差が出てきます。どちらも終の棲家(ついのすみか)としての役割が大いに期待できます。
「介護付き」「住宅型」ともに、24時間介護スタッフが介護を行い、胃ろうなどの医療行為のために看護師が夜間配置されているホームも増えています。介護度や医療依存度が高い入居者でもホームの中でケアを受けられるようになっています。そのほかにも、自由度が高く比較的介護度が軽度な人や自立度の高い人向けに、「カラオケルーム」や「温泉」などの娯楽設備の充実を図るホームも増えています。ただし、入居者の介護度が重度化したり、認知症を発症すると、退去や介護用居室への転居などを求められる場合があることには注意が必要です。
高齢者向け賃貸住宅もある
高齢者の住まいには、有料老人ホームのほかに高齢者向けの賃貸住宅もあります。2011年4月、高齢者住まい法の改正により、それまで3種類あった高齢者向けの賃貸住宅が廃止・一元化され、「サービス付き高齢者向け住宅」となったもので、略して「サ高住」もしくは「サ付」と呼ばれることもあります。
サービス付き高齢者向け住宅は、簡単に言えば、バリアフリーや居室面積原則25平方メートル以上という一定の基準を満たした「住宅」に、安否確認や生活相談サービスなどの「サービス」がついた高齢者向けの住まいです。高齢者住まい法によって、入居者の同意のない一方的な契約解除が禁じられていることが特徴です。
この住まいはまったく新しいタイプのものではなく、従来から一部にはありました。その一方で、バリアフリー化がなされておらず、安否確認や見守り体制も不十分な高齢者向け住宅も存在していました。そこで、高齢者が安心して暮らせる住宅を供給するために、その基準を定めたわけです。サービス付き高齢者向け住宅は、登場以降、急速に増加しており、今後も増加するものと見込まれています。
サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに比べるとゆったりとしています。居室の中に、原則として台所、トイレ、浴室、収納設備を設置すること、また手すりの設置、段差の解消、車椅子に対応できる廊下幅の確保など、3点以上のバリアフリーが条件です。
さらにサービスに関する基準として、緊急通報および安否確認サービス、職員の日中の常駐といった生活相談サービスが求められています。
これらはあくまでも最低限の基準ですので、運営事業者によっては、24時間介護職員を常駐させる、デイサービスや訪問介護事業所を建物に併設する、医療機関と連携を図りながら在宅医療を受けられるようにするなど、さまざまなサービスを取り入れようとしています。
サービス付き高齢者向け住宅は、まだ介護を必要としない人から要介護者まで、幅広く利用できます。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などの介護施設に比べて生活の自由度は高く、自分のペースで生活できます。しかし、住宅によって設備やサービスが大きく異なりますので、事前に調べておくことが大切です。
その住宅の中でどのような生活が送れるのか、また将来、介護が必要になった際にはどういったサービスが受けられるのか、それは安心できる体制なのか、などをしっかり見極めて選ばなくてはなりません。

老人ホームの費用はわかり難いと言われている。
有料老人ホームの費用はわかりにくいと言われます。有料老人ホームの費用は、家賃に当たる入居時費用と、管理費や生活費(食費など)に該当する月額利用料に分かれます。
入居費用について
入居費用は、入居時に一時金を納める「入居一時金方式」、入居費用を家賃ないし家賃相当額として月額利用料に上乗せして支払う「月払方式」、その二つから任意で選べる「選択方式」の3種類が主流です。そのほか、1年ごとに家賃相当額を前払いする「年払方式」を取り入れているホームもあります。
最近、新規開設される有料老人ホームは「選択方式」をとるケースが増えており、パンフレットにおいて、入居時の費用が「30万~3,000万円」などと大きな幅で表記されているのは「選択方式」を採用しているからです。
入居費用の支払方式は多様化しつつありますが、その権利形態については大半の有料老人ホームは「利用権方式」を採用しています。
利用権方式とは、各居室や食堂、浴室などの共用部、そのほかの生活支援や介護サービスなどを終身にわたって利用する権利に対価を支払うやり方で、その対価の全額または一部を前払金として入居時に納めるのが入居一時金です。入居費用が「月払方式」でも、権利形態が「利用権方式」の場合は、その対価を月額利用料に上乗せして月々支払うことになります。
ゴルフの会員権に似たシステムですが、会員権と違うところは、入居後、利用した期間に応じて、入居一時金が「償却」という有料老人ホーム独特の制度によって取り崩され、ホーム側に回収されていくことです。
一般に、入居時に初期償却として20%~30%程度が償却され、その後5年から長い場合は15年ほどかけて全額が償却されます。定められている償却年数以内に退去した場合は規定の金額が返還されますが、償却後は、退去しても返還金はありません。
要するに、入居一時金は毎月ないし毎年目減りしていく仕組みです。また、入居一時金は、「入居金」や「一時金」などホームによって名称が違うほか、その位置づけや償却率も異なっています。
月額利用料金について
一方、毎月支払う月額利用料は、主に施設の維持や人件費などの管理費と食費、光熱費から構成されます。食費は大半の有料老人ホームは、喫食した分のみの支払いですが、一部に厨房管理費として定額の費用が必要となるホームもあります。また光熱費に関しても定額制と実費精算制があります。
月額利用料は、これらの費用に公的介護保険の自己負担額が加わりますが、その金額は入居者の要介護度によって異なります。また、入居費用が「月払方式」の場合や、入居時に支払った入居一時金が「利用権」の全額前払いでない場合は、家賃ないし家賃相当額が月額利用料に加わります。
そのほか、ホームのなかには、介護サービスにオプション料金を設定している場合があります。たとえば、居室清掃や買い物代行、リネンのレンタル、規定回数以上の入浴は多くの場合、別途料金が必要です。どのサービスにどのくらいの料金がかかるのか、事前に把握しておくことが大切です。
上乗せ介護費
さらに「上乗せ介護費」が必要となるホームもあります。これは、有料老人ホームの人員体制の最低基準である「要介護者3名に対して介護スタッフ1名」を上回る配置がなされている際に発生するもので、スタッフの人件費に充てられます。なお、入居一時金に「上乗せ介護費」の利用権が含まれている場合もあります。
このように有料老人ホームの料金体系は複雑かつ多種多様です。料金の標準モデルというものも存在しません。費用を見積もる際は、料金に対する疑問や不明点を質問し、納得のいくまで説明を受けておくことが欠かせません。老人ホームへ入居した後に費用の支払いが困難なことが判明した場合には、別の有料老人ホームを探さなければなりません。

有料老人ホームのまとめ
高齢者のための住まいは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅のほかにも、高齢者向けの分譲マンションや公的介護保険の施設サービスと呼ばれる介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、認知症の人が生活する認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、ひとくくりにできないほど多様化が進んでいます。
選ぶ際には、入居予定者の身体状況や理想の生活と照らし合わせながら、必要な情報を集めて蓄積し、理想の住まいの形を思い描くことが大切です。
高齢者向けの住まいに関する情報は、雑誌やウェブサイト、新聞広告など、収集に困らないほど出回っています。述べてきたとおり高齢者の住まいは多種多様化しているうえ、費用も複雑です。入居してから“こんなはずではなかった”と後悔しないためにも、有料老人ホームなどの紹介事業者を活用するのも有効な手段です。
その人のニーズに合った有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を無料で紹介し、見学の取次もします。高齢者の住まいの情報を豊富にもつプロだけに、アドバイスも的確です。
単に紹介だけではなく、複雑な料金体系や、受けられる医療・介護サービス、公的介護保険の仕組みまで説明してくれるので、どやって老人ホームを探したら良いかわからないと不安を抱かれている方は、紹介事業者を活用してみるとよいかと思います。
(文:みんかいコールセンター 二見)
老人ホームの探し方
施設紹介センターの相談員として年間400件以上のご相談をいただきます。ご相談ご家族の9割以上の方が老人ホーム探しは初めて。一生に1度2度あるかないかの大切な選択が…今まさにおこっているという老人ホーム探しに少しでもお役に立てればと思います。

「介護度」の把握
私達相談員が、日々お客様から老人ホーム探しのご相談をいただく中で、必ず確認させていただく項目の1つに「介護度」があります。「介護度」とは、どのような介護サービスがどのくらい必要なのかを判断する基準となるもので、介護区分は「要支援1・要支援2」と「要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5」に分類されます。
老人ホーム探しでご来社いただくお客様にお父様やお母様の現在の介護度を確認させていただくと「介護認定を受けているのは知っているが、要介護の区分がはたして何なのかは分からない」「離れて暮らしているので、介護認定を受けているか受けていないかも不明」というご家族様も結構いらっしゃいます。
老人ホーム探しにとってこの「介護度」はホーム選びの際の判断基準の1つです。老人ホームの入居条件にはこの介護認定が要支援、要介護に該当しない「非該当」となった場合の「自立」の方から「要介護5」の方までを対象とした幅広い種類がありますが、中には一定の介護度以上でなければ入居ができないホームもあります。
老人ホーム探しにおいては「介護度」の確認が必須であること、また介護度をまずは確認されておくことで急な老人ホーム探しにおいても方向性がみえてくると思います。
介護認定を受けるにはどうしたらよいの?という方に。
介護認定を受けるには…。所定の手続き場所(市区町村の窓口や地域包括センター)にて申請を行い、後日認定調査員(市区町村の職員やケアマネージャーなど)がご自宅を訪問して、申請した本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りを行い、判定調査の結果、申請から1ヵ月程で要支援または要介護に該当するかどうかの結果を受けることができます。(入院中でも調査員が病院まで訪問し、認定調査を行ってもらえます)
この介護認定を受けることにより入居ホーム内においても食事、排泄、入浴、服薬管理などの「日常生活を送る上での支援」や「自立を助けるための支援」が介護保険サービスを利用して受けることが可能です。

身体状態の目安は?
《要支援1》・・歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的な動作を自分で行う事が可能で、かつ、薬の内服、電話の利用などの動作を行うことができる。
(要支援2)・・食事や排せつなどはほとんどひとりでできるが、立ち上がりなど日常生活の一部に手助けが必要で、その軽減や悪化予防のために支援を要する状態。
《要介護1》・・(部分的な介護を必要とする状態)身だしなみや居室の清掃などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
《要介護2》・・(軽度の介護を必要とする状態)立ち上がりや歩行、両足での立位保持などに何らかの支えを必要とする。排泄などに何らかの介助を必要とすることがある。
《要介護3》・・(中程度の介護を必要とする状態)身だしなみや居室の清掃などの身の回りの世話が自分1人ではできない。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
《要介護4》・・(重度の介護を要する状態)歩行や両足での立位保持などが自分1人ではできない。排泄がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下が見られる。
《要介護5》・・(最重度の介護を要する状態)寝たきりで排泄、食事、着替えなど日常生活全般において介助が必要。意思疎通が困難な状態。
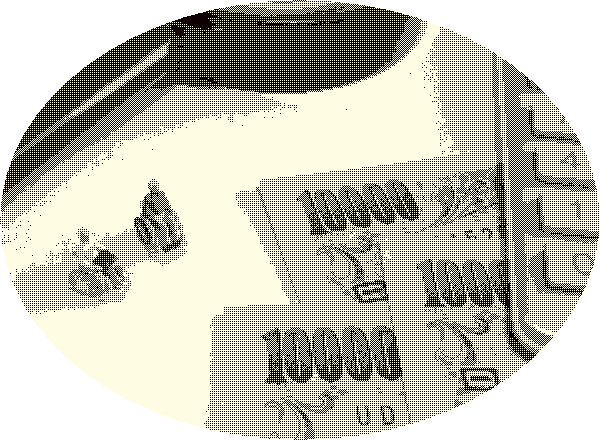
次に「入居条件」の整理をしましょう。絶対に譲れない条件とは
老人ホーム探しにおいてご家族が判断に悩まれる要因の多くが「今までインターネットで自分でも探してみたけれど、種類もさまざま、数も無数にあり、どんな違いがあるのか、何が違うのか、はたまたどこがあっているのか。何を基準に決めたらいいのか判断に迷う…」という声です。
確かにホームは星の数ほどあれど、老人ホーム探しにとって何より外せないのはご本人またはご家族のご希望条件とホーム側の入居条件もしくは入居対象の可否に合うかどうかこれを擦り合わせていくこと。こちらが大前提です。マンション選びとの大きな違いは希望するホームがすべて入居可能なホームに当てはまらない可能性があるということです。
例えば
「年齢」(60歳以上や65歳以上)(前述の)「介護度」また「身体状況」や「医療依存度」「保証人・身元引受人の有無」などホームは安心してお過ごしてしていだたくために安全面を考慮して十分なケアができるかを上記の状況を鑑みた上で入居判断を慎重に行います。そちらを踏まえた上で老人ホーム探しにおいて整理するポイントとなる代表的な条件(項目)には、⓵「入居時期」②「費用」③「立地(環境)」④「サービス内容・体制」⑤「施設の種類」があります。
細かく見ていきましょう。
⓵入居時期
(病院入院中)
・退院を余儀なくされ退院期日が決まっている
・すぐではないが退院をしなければならない など
(老健入所中)
・退所期間の3ヵ月が近づいている。ご自宅での生活は困難
(ご自宅で生活)
・お1人での生活はこれ以上心配ですぐにでも
・熱くなる夏前には
・将来的に検討したい など
②費用
・入居時に必要となる入居金一時金・保証金・敷金の有無
・月額利用料の上限
③立地(環境)
・なるべく面会にいけるよう交通至便のよい立地
・住み慣れた土地
・自然の多い環境
・費用面も鑑みて など
④サービス内容・体制
・人員体制
・医療体制
・リハビリ体制
・生活支援サービス(外出時の送迎・付き添いなど)の提供の有無 など
⑤施設の種類
《介護付き有料老人ホーム》・・一般的には介護が必要な65歳以上の方が対象の施設ですが、介護が必要のない自立の方が利用できる混合型の施設もある。介護職員が施設に常駐し、食事の提供・掃除・洗濯、買い物代行などの生活援助と入浴・排泄・などの身体介助サービスを提供。身辺介護は24時間体制で手厚い介護ケアが受けられる。
《住宅型有料老人ホーム》・・食事や掃除、洗濯などといった生活援助サービスが受けられる。施設内に介護スタッフが常駐していないため介護が必要になったら訪問介護や通所介護(デイサービスなど)の外部のサービスを受ける。要介護度の高い方や医療依存度の高い方など入居の対象にならない場合もある。また要介護度が重くなると月々の負担が割高になる可能性も。
《サービス付き高齢者向け住宅》・・60歳以上の方が入居できるバリアフリーな高齢者向けの賃貸住宅。安否確認と生活の相談、ご希望があれば食事のサービスも提供される。介護が必要になったら外部サービスを利用し生活できるが、介護度が高くなると住み続けるのが難しくなる場合もある。
《グループホーム》・・認知症をもつ方のための小規模な共同生活施設。施設のある市区町村に住民票がある方のみ入居できる。専門スタッフのサポートのもと、可能な範囲で炊事・洗濯・掃除など役割を持ち自立した生活を行う。

良いホームとは何?
老人ホーム探しの施設に対するご質問の中で「良いホームはどれですか?」と直球で聞かれることが度々あります。ズバリ聞きたくなるお気持ちはとても分かります。が、こちらの質問には明確にお答えできないのが正直な答えです。なぜならご状態もご状況もご希望もお1人お1人違うからです。
特徴のあるホームは往々にしてありますが、状況(身体状況)・条件(期日)・ご希望(費用・環境・立地・希望されるサービス内容)はご本人またご家族ごとにすべて異なります。Aさんにとってご安心のできる条件(ホーム)でもBさんにとっては同じ温度感を感じない現象は多分におこります。
ご本人・ご家族にとって感じられるgoodが「良いホーム」に定義付けされます。このことからも老人ホーム探しの2番目としては何を優先して、どこを外さない条件とするのかの入居条件をご家族内で整理しお話しされていくと老人ホーム探しにおいての選択されたい方向性に近づいてくると思います。
今回は2つのポイントをお伝えしました。少しでもお役にたてましたでしょうか?
最後に「百聞は一見に如かず」シリーズ(←初めて)から1つ
都内のある有料老人ホームを見学させていただいた時の出来事です。七夕のイベントで入居者の方が書かれた色とりどりの短冊がホーム内に飾られていました。
流麗な字が並ぶ中1枚の短冊に目が止まり見ると「私は最初入居することが本当に嫌でした。家族にも強く抵抗しました。3ヵ月が経ち周りのスタッフさんにもよくしていただきここが家のような居心地のよい空間になりました。これからは何か目標を決めてそれを成し遂げたいと思います」
施設長からこの短冊の入居者の方が90才だと伺いました。この声がご家族に届いているかは分かりませんが、何だかとても安心した気持ちになり、私も負けてられないなと自分を鼓舞した瞬間でした。
(文:みんかい関東エリア 高峰相談員)
健康寿命を意識した高齢者向け施設の選び方
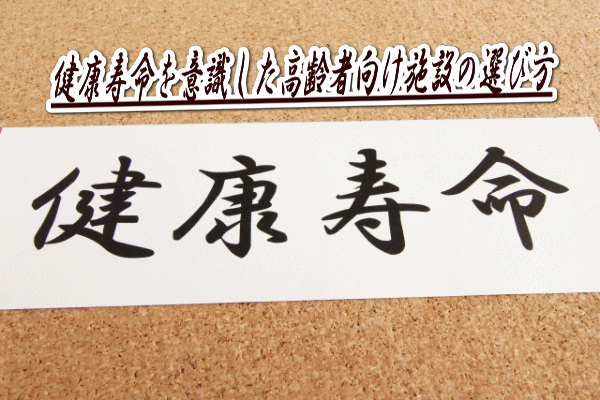
日本人の平均寿命は年々延びており、世界的に見ても日本は長寿大国としての地位を確立しております。最近、平均寿命と比較して語られるのが「健康寿命」という言葉です。施設へ入居した後もなるべく健康で過ごしたいという方に向け、健康寿命を意識した施設選びについて解説していきます。
私が高齢者向けの住まいの紹介センターの相談員を目指したのは「少子高齢化が進み、お体の不調や認知症等でお住まいに困る高齢者が増える中で、貢献できる仕事をしたい」という理由でしたが、率直に申し上げると「健康でなくなった高齢者の方を助けたい」ということです。この表現だけ見ると高齢者向けの住まいは「健康寿命が終わった方のための場所」になってしまいますが、これは大きな間違いであることが相談員を続けていく中で分かりました。これからの高齢者の住まいの適切な選び方について「健康寿命」という言葉を元に考えて参ります。
厚生労働省が定める健康寿命の定義について
そもそも健康寿命の定義って何でしょう?そう思ったので、健康寿命について調べてみました。日本人の平均寿命は2019年の厚生労働省の調査によると女性は87.45歳、男性は81.41歳です。日本人の健康寿命については、直近で2016年厚生労働省のデータしかございませんが女性が74.79歳、男性が72.14歳です。健康か不健康かの定義は、国民生活調査票(アンケート調査)に生命表を基礎情報として、サリバン法を用いて算出します。
主指標①「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」
→①に対し「ない」と答えた方を「健康」とする
副指標②「あなたの現在の健康状態はいかがですか」
→②に対し、「よい」「まあよい」「ふつう」と答えた方を「健康」とする
①と②を元に割り出されるのが「厚生労働省が定義する健康寿命」です。
※2019年の厚生労働省のレポートでは上記の算出の仕方に課題があるとしているため、今後定義の変更はあるかもしれません。

心の健康寿命という考え方
厚生労働省が定義する健康寿命の物差しで言えば、血液透析が必要な方、糖尿病で食事制限が必要な方、入院している方など、生きていくうえで行動に制限がかかっていると一律で「不健康」と認定されます。もちろんその通りかもしれませんが・・・。違和感を覚えるのは私だけでしょうか?
日常生活に影響する制限がありながら、夢に向かって仕事をし、結果を出して目をキラッキラさせながら生活している方もいれば、何も病気にはかかってはいないが、日常に生きがいを見つけることができずため息をつきながら過ごす方もいます。
身体的に健康か不健康かという物差しだけではなく、心理的に健康か不健康か(言い換えれば幸福に感じているか、不幸に感じているか)という物差しも必要に感じます。厚生労働省が定義する健康寿命を「体の健康寿命」として、「心の健康寿命」という考え方です。
※心の健康に関して言えば、鬱病などの精神的なご病気については厚生労働省定義の健康寿命関わってくるため、表現の方法については精査が必要です。あくまで便宜的な言葉として受け取って頂きたいです。
健康寿命を意識した高齢者向けの住まい探しを。
高齢者向けの住まいの相談の時に、「日常生活を送る上で手伝いが必要になり、自宅で住むことが難しくなったら入居を検討します」という方が多いです。高齢者向けの住まいは“健康寿命が終わってから入居する場所”と考えている方が多いと感じます。はっきり言って勘違いです!もったいないです!!実は高齢者向けの住まいは心身の健康寿命を延ばす可能性を秘めているのです。

具体的な建物やサービス内容とは?
例えばサービス付き高齢者向け住宅は、お部屋の中にキッチンやお風呂、洗濯機置き場もあり外出も自由で、マンションと変わりないような生活を送ることができる物件が多いです。中のサービスとしては、1日1回以上安否確認サービスが付いており、お部屋で何かあった時も駆けつけてくれるスタッフの方が最低日勤帯は常駐しております。
お一人暮らしの高齢者の方がサービス対高齢者向け住宅に入居すれば、お体に何かあった時も住宅のスタッフが発見してくれるため、病気やお怪我の重篤化を予防し「体の健康寿命」を延ばすことができます。またサービス付き高齢者向け住宅にはオプションで食事をつける事ができるため、買い物や料理、片付けに使っていた時間を趣味の時間や住宅の中でのお友達との交流の時間に充てることができます。これで「心の健康寿命」を延ばすことができます。
「でも介護付き有料老人ホームは元気じゃなくなった時に入るところでしょう?」それも勘違いです!もったいないリターンズ!!介護付き有料老人ホームは、介護士と看護師が毎日勤務しており、夜中も含めて24時間体制で見守りとお手伝いが可能です。このサービス内容を見ると「やっぱり健康ではない方のための住まいでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし最近は「健康な方」や「健康になりたい」方向けの介護付きホームも増えてきております。まずイベントごとです。サービス付き高齢者むけ住宅と比較すると介護付き有料老人ホームは、ホームの中でのイベントが多い傾向にあり、お友達が作りやすく、楽しく日々を過ごしたい方はご自宅より楽しみが増える可能性が高いです。コロナ渦で少し自粛傾向ではあるものの、ホーム事で様々な取り組みが行われております。

例えばバーカウンターがあるホームでは、夜にお酒を飲んで語り合う夜レクリエーションや、囲碁将棋などのクラブ活動、ホーム内に人工温泉があるところなど、心の健康寿命を延ばす事ができる内容のホームが増えてきました。また、看護師や往診のお医者様による健康チェックや緊急時の対応は「体の健康寿命」を延ばすことに繋がります。
他にも食事にこだわりがあり、健康的でありながら美味しい食事が提供されるホームもあれば、リハビリが充実しているホームでは集団体操やスタッフが付き添っての散歩、専門家による個別のリハビリが提供されます。食事やリハビリのサービスが充実しているホーム入居することは、「心」と「体」の健康寿命どちらも延ばすことに繋がります。
介護付有料老人ホームは心の健康寿命を延ばせる!?
介護付きホームも「健康寿命」を延ばす可能性を秘めている事がお分かり頂けたかと思いますが、さらに真価を発揮するのは「体の健康寿命が終わってしまった」方に対してだと私は思っております。厚生労働省が定める健康寿命では「要介護2以上」の方は不健康とみなされてしまいますが、介護付きホームに入居すれば、「心の健康寿命」を延ばすことができる可能性があります。

歩行の不安定などお身体が理由で要介護度が出ている方の場合、先にお伝えしたリハビリやマッサージが提供できますし、生活しづらい部分をお手伝いして頂けます。バリアフリーの環境なので、自宅では使えなかった車椅子移動を選ぶことで、痛みから解放されてゆっくり過ごすことができるかもしれません。認知症が理由で介護度が出ている方の場合、ご自宅では認知症の影響による行動で「問題行動」と認識されて家族から怒られる事が多かった方が、認知症の対応に優れている介護付き有料老人ホームに入ることで優しく否定されずお世話をして頂き、ご自宅にいた時より穏やかな気持ちで過ごすことができるケースがあります。
健康的な生活を送る事が出来る施設選びを。
高齢者向けの住まいをどのように探せばいいのか、迷う方が多いですが、健康寿命の観点から考えると住まい探しの指標の一つが見えてまいります。現在ご自身の体の事で心配がある方は「体の健康寿命」を延ばすサービスを提供してくれる住まいを探せばいいです。体はお元気ですが「今の生活が楽しくない」「生きがいをもって過ごしたい」という方は、心の健康寿命を延ばすことができるサービスを提供してくれる住まいを選べばいいのです。
サービス付き住宅であれ、介護付きホームであれ、高齢者向けの住まいには心身の健康寿命を延ばす力があると確信しております。「お手伝いが必要になってから相談に行こう」と思っていらっしゃる方も、一度健康寿命を延ばすための場所として高齢者向けの住まいを探してみませんか?
老人ホームが必要となる具体的な実例も紹介
身体低下と共に変わる生活~老人ホームが必要となる具体的な実例も紹介

皆様、高齢者やその家族が老人ホームへの入居を考え始めるタイミングは、どんな時でしょうか。そして、数ある中からどのように入居する老人ホームを決めるのでしょうか。老人ホーム紹介センターに相談にいらっしゃる方に多いのは、ご自身の親についてお悩みを抱えているケースです。
例えば、
① 相談者の親御さんが、ある日、自宅内あるいは買い物などの外出時にバランスを崩して転倒してしまい、大腿骨頸部や大腿骨転子部を骨折、つまり太ももの骨の股関節部分を骨折してしまったという相談。
② 入院して手術をしたばかりなのに2週間後に退院してほしいと病院側から言われ、非常に切羽詰まった状況での相談。

骨折してしまうことで変わる生活
高齢者の骨折はADLの低下を招きます。ADLとは、日常生活動作のことを指します。具体適には「歩くこと」「着替えをすること」「入浴すること」など、日常生活を送るうえで欠かせない基本的な動作のことです。特に大腿骨など下肢の怪我は生活に大きく支障をきたし、特に高齢者は一人で生活を送ることが困難になり、場合によっては寝たきりになってしまう危険性もあります。
そのため、骨折で入院した後は、できるだけ早く骨折した部分を金属で固定する手術や、股関節部分そのものを人工骨頭に置き換える手術を行います。しかし、ご年齢や体調が優れない場合、麻酔の負担に耐え得る体力がないなどの理由によって手術が行えない場合もあります。その場合は骨がくっつくまで長期間ベッドで安静にしていなければいけないので、その間に筋力、特に下肢筋力が衰えてしまい寝たきりになってしまうことがあります。
また、毎日ベッドの上で過ごすうちに時間や曜日の感覚が薄れ、認知機能も低下してしまい認知症を発症する方もいます。運良く手術を行えた場合は、できるだけ早くリハビリをはじめて寝た切りを予防しますが、それでも骨折前と同じようには歩くことができなくなり、杖や歩行器や車椅子が必要となる場合があります。

自宅まで階段を使う生活環境の方は注意
最近はバリアフリー住宅も随分と普及していますが、高齢者の生活環境はまだまだ大小さまざまな段差に囲まれています。エレベーターが設置されていない集合住宅で生活されている方もいて、スーパーなどへの買い物や病院への通院、何をするにも階段や道路の段差が障害となって負担を感じ、せっかくリハビリを頑張って退院してもだんだんと外出自体が億劫となり引きこもるようになってしまった結果、さらにADL・日常生活動作の機能を低下させていきます。
子供達が近くに住んでいれば手助けをしてくれることもあるでしょうが、子供達にも日々仕事があり、それぞれの家庭、それぞれの生活があるため、今の時代「同居」という選択肢を選ぶことは難しく、また毎日通って親の生活の支援をするというのも現実的に難しいでしょう。
老人ホームを探すこと

一言で老人ホームといっても、介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの種類があり、身体の状態や、認知症がある方、ない方などで、合う、合わないといった問題もあります。かかる費用やヘルパーなどスタッフの人数、レクリエーションが多いとか、少ないとかなどの違いもあります。
老人ホームの費用はどのぐらいかかるのだろうか、親の年金の範囲でおさまるのだろうか、さまざまな不安を抱えて老人ホーム紹介センターに足を運んでくださるのです。老人ホームに入居されるご本人様が、「終活」と称して自宅で生活できなくなった時を想定して事前に老人ホームを探すということもございますが、何かあったらここにしようとしっかり決められている方は少ないです。
そもそも、事前に目星をつけて気に入った有料老人ホームをみつけていても、いざというとき空室があるのか、実際に入居ができるのか、その時になってみなければわからないのです。なぜなら、有料老人ホームには「入居要件」がございます。
基本的に65歳以上という年齢や介護認定を受けていることなどが挙げられます。怪我をしてADLが低下してから、どのような身体介護が必要になっているのか、看護師による医療的な処置が必要なのかなどは事前にはわかりません。多くの方は自分の親が喜んでくれるような老人ホームを探したいというお気持ちを強くお持ちですが、一体何を重視して老人ホームを探せばいいのでしょうか。
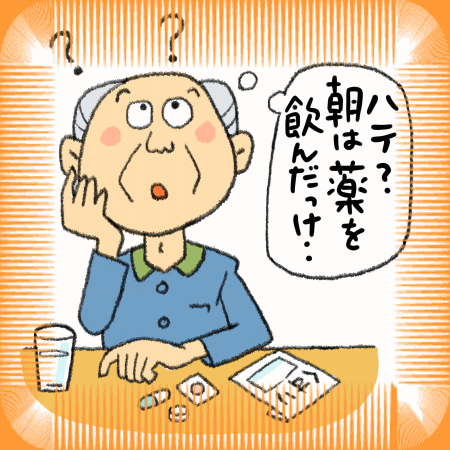
具体的な事例
「皆さん、一体どうやって老人ホームを決めているのですか?」と、ご相談に来られる方は質問されますが、答えは1つではありません。人によって、家族によっても有料老人ホームに求める大切な点はそれぞれ違います。
例えば、「うちの母親は認知症もない、ちょっとした転倒から骨折してしまって歩行器が必要となったけど買い物が負担になっているだけだから、まだまだ今と同じように元気で自立した生活を送ってほしいので、何でもかんでもやってくれるところだと返ってよくないのでは」。そうおっしゃるご相談者ですが、話を聞いていくと入居対象となるお母様の年齢は90歳を過ぎており、以前は多趣味でいろいろなサークル活動に参加するため毎日外出していたのに、最近はお惣菜を買いに行くのが精一杯で、家にいるときはずっとソファに座りっぱなし。テレビをつけてはいるものの本当に観ているかどうかはわからず、時々おトイレに行くのも間に合わなく失敗してしまう。昼夜問わずに毎日息子様に電話して、あれがない、これがないと失くし物の相談をされているご状況でした。
果たして、この方の自立した生活を支援とは、どのようなポイントが大切になってくるのか。息子様が認識しているお母様のご状況は、本当に元気で自立した生活といえるのか。老人ホームへの入居を考えるとき、入居費用や月額費用、場所などもとても大切です 。ただ、それ以上に今どのような手助けを必要としているのか、今後どのような手助けが必要となってくるのか、いま目の前にいる親が何を必要としているのかをできる限り知ることも大切です。正確に認識することが大切です。

介護付有料老人ホームで過ごす生活とは
介護付有料老人ホームは、24時間介護資格を持ったヘルパーが常駐し、掃除や洗濯、食事も上げ膳据え膳でお手伝いしてくださいます。かわりに、今まで自分のペースで送っていたご生活は、食事の時間や入浴の時間・回数をホームの都合に合わせた時間割りに添って過ごすことになります。
しかし、有料老人ホームには24時間ヘルパーがいるので、昼でも夜でも不安なことがあれば話を聞いてくれる人が近くにいます。もちろん、ヘルパーは介護という多忙な仕事をしているわけですから、常に話し相手をできるわけではないです。しかし、「部屋の中にあれがないの、誰かに盗られてしまった」と言えば、「では、後で一緒に探しましょうね」。と言うことができます。
毎日、朝昼晩の食事の前に「お手洗いは大丈夫ですか? 一緒におトイレに行きましょう」。と声をかけてくれる人がいるから、間に合わなくて失敗してしまうということも減っていく可能性があります。食事以外にも、「今日は皆さんで絵葉書を作ってみませんか?」、「今日は皆さんで体操を頑張りましょう!」と、ただソファやベッドの上で座っているだけの時間に声をかけてくれる人がいます。
本人としっかり向き合うことの大切さ
いま、自分の親が何を本当に必要としているのか、本当は何を求めているのか。そのことに気づいてあげること、理解してあげることがとても大切なことだと思います。その気づきや理解の深さが納得のいく老人ホーム探しの大きなポイントです。ご両親やご家族様の老人ホームへの入居を考えるとき、まずは入居を必要とする方の状況をよく知ってください。そこからがスタートです。そして、老人ホーム紹介センターにぜひともご相談ください。お母様、お父様が何を必要とされているかをお伺いし、どのような老人ホームがご希望に合っているのか、納得のいくホーム探しをお手伝いさせていただきます。
(文:みんかい関東エリア 入江相談員)
老人ホーム入居先を選ぶ際の注意点
老人ホームの入居先を選ぶ際の注意点
皆さんはご家族、ご自身が「老人ホームへ入居する」という事について、どれだけ真剣に考えたことがあるでしょうか。自分の両親が元気なうちには全くと言ってよいほど、老人ホームに入居する、入居させることなど想像もしないことだと思います。今回は、老人ホーム探しをする上で注目すべき項目についてご紹介させていただきます。

老人ホームの入居先をどのように探すか。
老人ホームを探す際に様々な方法で調べると思いますが、私たちが行っている「老人ホーム紹介会社」を利用される方は年々増加傾向にあります。しかし、一般の方で老人ホーム紹介センターという存在をご存じの方はまだまだ少数だと思います。いざ、ご家族やご自身に介護が必要になった時に、ゆくゆくは介護施設(老人ホーム)への入居を検討することになるかもしれませんが、どう探していけばよいのか?
誰に相談できるのか?自分では何から手を付ければ良いのかわからない!そういった方々に、大切なご両親、ご家族様の今の身体状況、今後の身体状況、さらにどのような老後を過ごしていくことが出来る老人ホームがあるのかをご提案しております。一口に老人ホームと言っても、様々なタイプがあります。何を基準にして老人ホームを探していけばよいのか、とても難しい問題です。
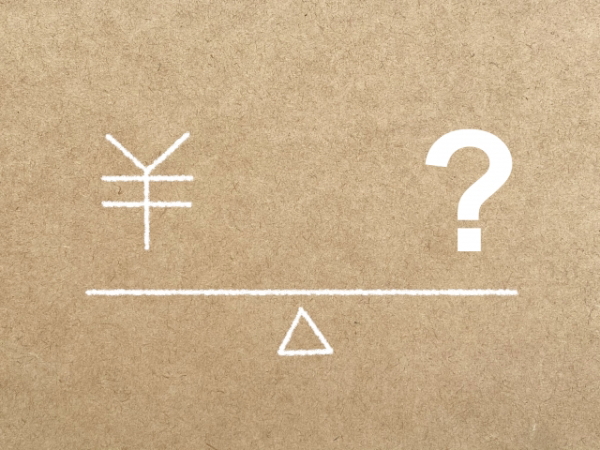
具体的にどうすればよいのか。
希望の場所、予算、医療体制、レクリエーション、リハビリなど検討する項目はたくさんあります。今は一昔前とは異なり、インターネットの環境もあり、パソコンが無くてもスマートフォンがあればご自宅でもどこでもすぐに調べることができるようになっています。老人ホームの紹介センターも多数存在し、どこの紹介センターを選ぶのかだけでも迷ってしまうくらいです。
そんな気軽に老人ホームを調べたりできるのだから、わざわざ老人ホーム紹介センターなどというものを使う必要はないのでは?と思われるかもしれません。実際に老人ホームをインターネットで検索してみてください。
確かに、老人ホームの場所、費用などは簡単に検索が出来ます。見栄え良くホームページも作られており、なんでも希望が叶えられるのでは?と思えます。しかし実際にはその中から、本当にご両親、ご家族に合っている老人ホームを探し出すことは容易ではないということがおわかりになるかと思います。

入居先を探すことが容易ではない主な要因。
① 老人ホーム入居の場所選び
今は核家族化で、大人数でひとつ屋根の下でのご生活をされている方は少なくなっています。当然、老人ホームに入居を検討されているご兄弟やお子様世代、お孫様世代の方は別々の地域でご生活されている方が多いのではないでしょうか。
そんな中、ご入居された後にご本人への面会や入院時の対応なども出てきます。ご家族皆様がそれまで在宅での介護に関して、平等に関わってこられているとも限りません。キーパーソンとなられている方がいらっしゃると思います。その方がメインで色々な対応をされていたとすれば、なにか急を要する状況になった際に、すぐに駆け付けることが出来る場所、またはご本人が永らくお住いになっていたことがあるなど愛着がある場所、自然がお好きで山や海が見える環境など様々に考えられます。
実際に入居のご相談を伺っている中で、別々の場所にいる家族の中間地点が良いのではないか?というお話もあります。そういう時には、私はキーパンソンとなっている方のお住いに近い場所をお勧めしています。夜間にご本人が急変し、老人ホームや搬送先の病院に行く必要があった場合、夜中なので公共交通機関は動いていません。タクシーや自家用車で動ける範囲が安心できる場所になるかもしれません。

② 老人ホーム入居の予算
予算に関しては、老人ホームを選ばれるときに一番重要になる部分かと思います。正直、入居に関する費用はピンからキリまでです。先ほど【老人ホーム入居の場所選び】でキーパーソンとなる方の近くが良いのではないかと書きましたが、特に東京23区のいわゆる高級住宅地のようなエリアでは、家賃が高額になります。
想像してみてください、利便性も良く、環境も良い一等地と呼ばれる場所で戸建て、マンションを購入または賃貸で住むとします…。土地の価格が高いため、当然賃料も高くなっていると思います。老人ホーム毎月の費用には、部屋の賃料、食費、サービス費などなど老人ホームにより多少中身は異なるものの、大きなウェイトと占めてくるのが「賃料」です。
この「賃料」が場所によって通常の戸建て、マンションのように開きが出てくる部分です。施設運営会社が同じ老人ホームであっても、場所が違えば当然毎月の費用にもこの差が生じます。建物や介護内容、その他が同じでも異なる費用の場合がほとんどですので、予算を重視される場合には、気に入った老人ホームがあるが費用面で悩まれるときは、都心か多少離れても賃料分が安く、それでも内容は同じ郊外にある同運営企業の老人ホームを選択するのも良いかもしれません。また、老人ホームに入るには最初にかかる費用、いわゆる入居金が高いのでは?と思われるでしょう。
確かに昔は必ずと言ってよいほど入居金がありました。現在は入居金(賃料の前払いという性質)を支払い、毎月の費用を抑えられるプランや、入居金は0円で月々のみの支払いでご入居いただけるプランを選択できるようになっている老人ホームも多くなっています。数年分の賃料(多くは5年分程度)を前払いしてしまうため、その間の毎月の費用を抑えることができます。多くは5年程度の償却期間で入居金は毎月均等に償却されていきます。償却期間内でのご退去があった場合には、残りの月数に応じて返還金がきちんと発生します。
また、ほとんどの老人ホームでは、償却期間終了後には再度の入居金の支払いは必要無く、初めに選んだプランの月額費用でその後も継続入居できるため、ご年齢も若く、長くご生活されることが想定される場合には、結果として費用の総支払額を抑えることができるようになっています。
逆にご病気などで、いつご入院によって、元いた老人ホームに戻れなくなるかわからないという方や、100歳に近いご高齢の方で今後5年以上のご入居はあまり現実的ではないという方が入居金をお支払いするプランを選択する大きなメリットは少ないと思います。多少毎月の費用が高めに見えても、月払いのプランが選択可能な老人ホームであれば、そちらを選択する方が良い場合もあります。その方がどれだけの期間お住いになるかは正直わかりませんが、ご年齢やご病気、ご予算などを考えながらご紹介させていただいております。

③ 医療対応・レクリエーション・リハビリなど
ご入居されるご本人のご病気、趣味やリハビリを必要とするのかそうではないのかによっても、老人ホームの選択は変わってきます。多くの老人ホームでは看護師が朝の8時台から19時頃までのいわゆる日勤帯で常駐しています。よくあるのが、食事が飲み込むことが難しく、直接胃にチューブから栄養を流し込む「胃ろうと」呼ばれるような経管栄養の方は、たんが絡みやすくなり、吸引が必要になります。
この行為は、医療行為にあたるため看護師が行わなければなりませんが、一部の老人ホームでは看護師以外に、研修を受けた介護職員が行っている場合もあります。頻度にもよりますが、看護師がいるときだけに必要とも限りません。そんな時は看護師が24時間常駐する老人ホームや、研修を受けた介護職員が夜間帯もいる老人ホームを選択する必要があります。
ご本人のこれまでの趣味や、脳梗塞などの後遺症により継続したリハビリが必要だという方には、お好きな趣味に関するレクリエーション活動がどのように行われているのか、リハビリの専門家(理学療法士や作業療法士、柔道整復師)による集団、個別のリハビリが受けられるのかなどの確認も必要です。
(文:みんかい事業推進部 松野)